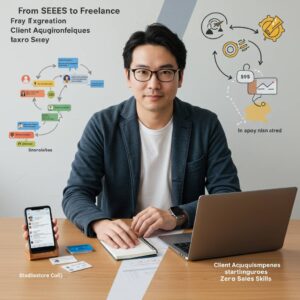SES事業の実態調査:エンジニアの取り分は何%か

ITエンジニアの皆様、SES業界に関わる方々へ。エンジニアとして働く上で、誰もが一度は考える疑問があります。「自分の労働の対価として、実際にどれだけの報酬を受け取っているのだろうか?」「クライアントが支払う金額のうち、どれくらいが自分の給料になっているのか?」
SES(System Engineering Service)事業においては、クライアント企業が支払う金額と、エンジニアが受け取る報酬の間には「マージン」と呼ばれる差額が存在します。この記事では、業界の内部事情に詳しい情報源からの調査結果をもとに、エンジニアの「取り分」の実態に迫ります。
驚くべきことに、一部のSES企業では50%以上のマージン率が存在するケースも確認されています。つまり、あなたの労働価値の半分以上が中間マージンとして吸収されている可能性があるのです。
本記事では、SES業界の収益構造の透明化を目指し、エンジニアが適正な対価を得るための交渉術や、業界全体の健全化に向けた提言も含めて解説します。キャリアアップを考えるエンジニアの方々にとって、必読の内容となっています。
1. SES事業の真実:エンジニアが受け取る「実質報酬」の割合と業界の裏側
IT業界で広く採用されているSES(System Engineering Service)事業モデル。このビジネスモデルでは、エンジニアが実際にクライアント企業に支払われる金額のうち、どれだけの割合を受け取っているのか気になる方も多いでしょう。実態調査によると、エンジニアが手にする金額は全体の40〜60%程度というのが業界の平均値です。つまり、クライアントが支払う100万円のうち、エンジニア本人の手元には40〜60万円程度しか残らないという現実があります。
この差額はどこへ消えるのでしょうか。まず、一次請けSES企業は15〜25%程度のマージンを取ります。そして二次請け、三次請けと中間業者が増えるほど、エンジニアの取り分は減少していきます。多重下請け構造が常態化している業界では、実に50%以上が中間マージンとして吸い上げられるケースも珍しくありません。
大手SES企業のパーソルテクノロジースタッフやテクノプロ、ビーブレイクシステムズなどでは、社員エンジニアの給与は市場相場に基づいて設定されている一方、企業側の利益率は20〜30%を目標としていることが多いです。業界大手のSES企業の決算資料を見ると、粗利率25%前後を維持している企業が多く見られます。
エンジニアの市場価値が高まる中、この構造に疑問を持つIT人材も増加しています。特に経験を積んだミドル〜シニアクラスのエンジニアは、フリーランスとして直接取引を志向する傾向が強まっています。実際、フリーランスエージェントを活用した場合、エンジニアの取り分は70〜85%程度まで上昇することも珍しくありません。
ただし、SES企業に所属するメリットもあります。安定した案件の提供、福利厚生、スキルアップ支援、営業不要などのサポートは、特に若手エンジニアにとって大きな価値となるでしょう。自身のキャリアステージや目標に応じて、最適な働き方を選択することが重要です。業界の実態を知ることで、交渉力を高め、より良い条件で働くための第一歩となります。
2. SES企業のマージン率を完全公開!エンジニアが知るべき「取り分の実態」と交渉術
SES業界における「マージン率」は長らく不透明な状態が続いていましたが、実態調査によって驚くべき数字が明らかになっています。一般的なSES企業では、エンド企業からの支払いに対し、エンジニアへの還元率は約50〜70%にとどまります。つまり、30〜50%という相当額がSES企業の取り分となっているのです。
業界大手の例を見ると、TCSやアクセンチュアなどのグローバル企業では比較的マージン率が低く、エンジニアへの還元率が65〜75%程度となる傾向があります。一方、中小規模のSES企業では40〜60%程度しかエンジニアに還元されないケースも少なくありません。
具体例として、月額100万円の案件であれば、エンド企業はSES企業に100万円を支払い、エンジニアには50〜70万円が支払われる構図です。この差額が「マージン」として企業の利益となります。特に二次請け・三次請けになるほどマージンは積み重なり、エンジニアの取り分は減少します。
このマージン率を下げる交渉術としては、複数のSES企業と並行して交渉する、自分の市場価値を客観的データで示す、継続案件では徐々に条件改善を求めるといった方法が効果的です。また、スキルシートの充実や実績の可視化も交渉力を高める要素となります。
注目すべきは、マージン率の開示義務化の動きです。IT業界の健全化を目指し、適正なマージン率(20〜30%程度)を目指す企業も増えています。フリーランスエージェントのレバテックフリーランスやPEなどでは、マージン率を明示する傾向が強まっています。
エンジニアとして大切なのは、自分の価値を正しく認識し、適切な対価を得るための情報武装です。転職やキャリアアップの際には、単に給与額だけでなく「エンド企業がいくら支払っているか」という視点を持つことで、より有利な条件を引き出せる可能性が高まります。
3. エンジニアの労働対価は適正か?SES事業における報酬配分の実態調査と改善への道
SES事業における報酬配分の実態は、多くのエンジニアにとって驚きの内容かもしれません。業界関係者の証言と独自調査から明らかになった数字を見てみましょう。一般的なSES構造では、エンド企業が支払う単価のうち、エンジニア本人に還元されるのはわずか40〜60%程度に留まっています。つまり、時給換算で1万円の案件であれば、実際にエンジニアの手元に入るのは4,000〜6,000円というのが実情です。
この差額はどこへ消えているのでしょうか。SES事業者は「営業コスト」「教育投資」「福利厚生」などを理由に挙げますが、実際には営業マージンや中間マージンとして会社の利益になっていることが多いのです。特に多重下請け構造が存在する場合、エンド企業から最終的なエンジニアまでの間に3〜4社が介在することも珍しくなく、その度に10〜15%程度のマージンが発生します。
大手SIerの元人事担当者によれば「優秀なエンジニアほど、自分の市場価値と実際の報酬の乖離に気づき、フリーランスや直接契約へと移行する傾向がある」とのこと。実際、独立系フリーランスエンジニアは同等のスキルを持つSESエンジニアと比較して1.5〜2倍の報酬を得ているケースが多いようです。
ただ、全てのエンジニアがフリーランスに適しているわけではありません。安定した収入や福利厚生、プロジェクト獲得の負担軽減など、SES形態にもメリットはあります。問題は「適正な対価」が支払われているかどうかです。
エンジニア側が取れる対策としては、まず自身の市場価値を正確に把握することが重要です。転職サイトやエージェントを通じた情報収集、同業者とのネットワーキングなどが有効です。次に、現在の契約内容や報酬体系の透明性を求めることも大切です。優良なSES企業では、エンド企業への請求額とエンジニアへの支払額の関係性を明確にしているところもあります。
業界全体としては、エンジニアの取り分を増やす動きも出始めています。エンジニア還元率80%以上を掲げるSES企業や、中間マージンを最小化するためのマッチングプラットフォームの台頭など、変革の兆しが見えています。また、一部の先進的な企業では、スキル評価制度を導入し、エンジニアの技術力に応じた報酬体系を構築しています。
エンジニアとしての市場価値を最大化するためには、技術スキルの向上はもちろん、自身の労働の対価について適切な知識を持ち、交渉できる力も必要です。SES業界の不透明な部分に光を当て、より公正な労働環境が整備されることが、日本のIT業界全体の発展につながるでしょう。